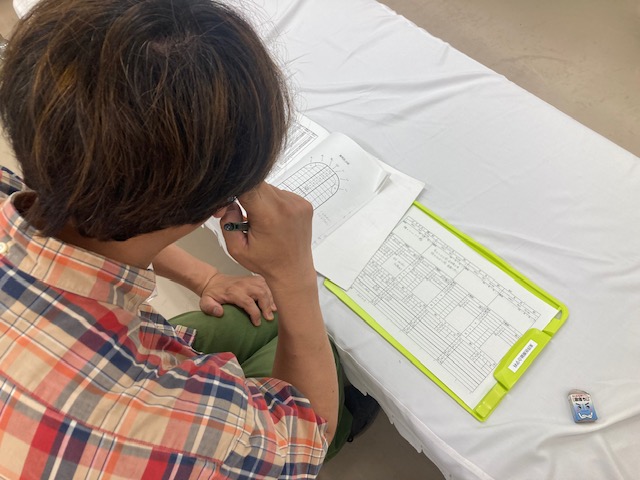積聚治療における背部の兪穴(背中のツボ)のより効果的な使い方について、3回に分けて、解説されました。この3回の講習会の内容について3回まとめて復習していきたいと思います。
積聚治療では、ラインの選択、道具の選択、治療方式の選択という3つの選択が複雑に絡み合い、劇的な治療効果が発揮されます。
まず、第3回の講習会では、積聚治療における背部兪穴(背中のツボ)の使い方、特にラインの選択に焦点を当てて、その劇的な効果を引き出すための工夫が解説されました。
積聚治療では、背部のラインにはそれぞれ意味付けがありました。
2行線:基本治療として用いる。最も腹部に近く陰的
1行線:2行線の同様の位置づけ。2行線で不足している分を補う目的で用いる。
脊際:督脈と同じ位置づけ。指標に左右差がある場合(秩辺・肩・脊際)に用いる。
督脈:背部を陽面とすると、極陽となり、深部で陰の気と接している。また左右の気の接点でもあるので治療の影響が大きい。2行線に加えて補助治療として使うことが多い。
そのラインをどう組み合わせていくかも重要なポイントでした。病症を判断し、2行線を基本に他の3ラインを組み合わせて使います。
2行線+1行線:指標の変化が十分だが、もう少しツボを用いた時。陰の虚病症
2行線+脊際:指標に左右差がある場合(秩辺・肩・脊際)陽の実病症、陰の実病症
2行線+督脈:陽の実病症、陰の実病症、陽の虚病症
背部治療の原則は
① 2行線は4穴必ず用いる。
② 1ライン1領域1穴のみ用いる。
③ 最多8穴となる。(2行線4穴+1ライン4穴)
④ 鍼以外に、督脈は透熱灸と知熱灸、脊際には知熱灸が用いられる。
ということで、実技は、背部治療2行線+督脈を使用し、お互いの治療を行いました。
カルテに記入することも徐々に増えてきていますね!
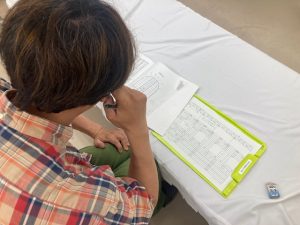
次回は、道具の選択についてです!